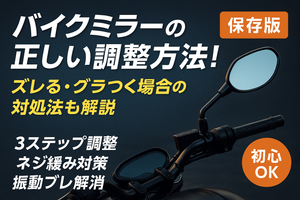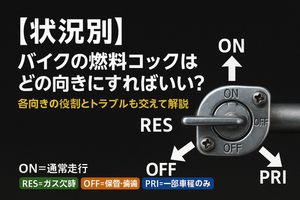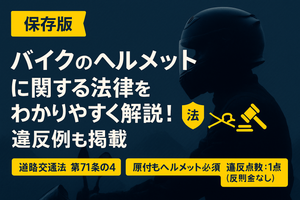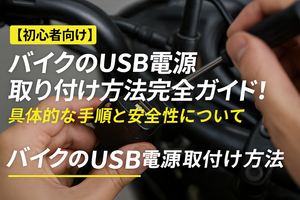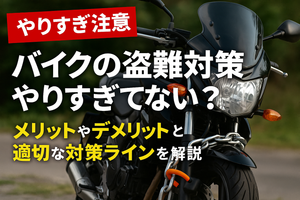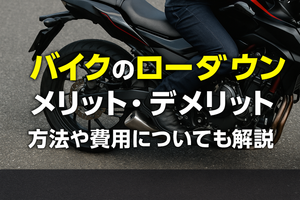バイクの走行距離は寿命と関係する?乗り換える際の目安は何キロか、長く乗るためのコツも解説

【前提】バイクの走行距離は寿命の目安として考える

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/93-1839003/
バイクの寿命を考える上で参考になるのが走行距離で、大まかな目安として5万~10万kmが一つの目安です。
バイクのクラス(原付、大型など)や車種によって寿命の目安となる走行距離に差がありますが、ほかにも乗り方や取り扱い方によっても、バイクの寿命は変わってきます。
走行距離
中古車で購入した場合など、寿命の目安となるのが走行距離で、バイクのクラスが大きくなればなるほど、寿命になるまでより多くの距離を走行できる傾向にあります。
例えば、原付一種(50ccクラス)だと5万km前後が寿命の目安ですが、1,000ccを超える大型バイクだと、8万~10万kmが寿命の目安です。
また同じ5万kmでも、短期間で5万km走行した場合と長期間で5万kmに達した場合とでは、長期間で達したほうがバイクの劣化も進んでおり、より寿命が近いです。
保管環境
走行距離以外にも、バイクを保管(駐輪)しておく環境によっても、寿命に違いが出てきます。
屋外で雨ざらしにして保管していると、雨水や風などでパーツの劣化が進んで寿命も短くなるので、屋外で保管する場合はカバーをかけるなど、雨風にさらされるのを避けるのがオススメです。
直射日光もパーツの劣化を進める原因になるので、よりバイクの寿命を伸ばしたい方は、可能ならばガレージなど、屋根の付いた場所で保管しましょう。
点検の頻度
バイクを定期的に点検し、オイル交換などのメンテナンスをしっかり行っていると、バイクの寿命も延びます。
逆にオイル交換や洗車を定期的に行わない場合は、エンジン寿命を短くし、バイクの車体にサビが発生するのも早いです。
定期的にバイクを点検し、オイル交換などのメンテナンスをしっかり行えば、バイクの寿命も伸びますし、サビやパーツの劣化にも早く気づけ迅速な処置もできます。
バイクの取扱い
バイクの乗り方などの取扱いによっても寿命が変わり、急加速や急ブレーキなど、急のつくラフな運転を続けていると、バイクの寿命も短くなる傾向にあります。
急加速などを続けるとバイクに負担がかかり、バイクの寿命を短くするだけでなく事故などのリスクも高まり、事故を起こすとなおさらバイクの寿命を短くする結果に。
普段から穏やかな運転を心がけ、丁寧な操作を意識すればバイクへの負担も少なくなり、寿命も長くなります。
時間に余裕が無いと荒い運転になりやすいので、時間にも余裕を持たせ、安全運転を心がけていきましょう。
【排気量別】バイクの寿命の目安となる走行距離

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/AF-8142649/
バイクの寿命は保管環境や点検の頻度、乗り方など様々な要因によって変わってきますが、中でも特に判断材料となるのが走行距離です。
バイクの排気量(クラス)別に、目安となる走行距離を表にまとめましたので、ざっくり走行距離を知りたい方は、表を参考にしてみてください。
| バイクの排気量 | 寿命となる走行距離の目安 |
| 50cc原付 | 3万km~5万km |
| 125cc小型 | 5万km |
| 250cc中型 | 5万km~8万km |
| 400cc~大型 | 5万km~10万m |
| 2ストエンジン車 | 1万km~3万km |
50cc原付バイク
50cc原付一種クラスのバイクの寿命の目安は、3万km~5万kmです。
50ccクラスはエンジン出力や最大トルクの関係で、エンジンを常に高回転にして走行するケースが多く、ほかのクラスよりエンジンへの負担も大きいため、寿命も短くなっています。
日頃からしっかりオイル交換や洗車などのメンテナンスをしっかり行えば、5万kmが寿命ですが、50ccユーザーはメンテナンスの知識があまりない方も多く、2万~3万km程度で寿命を迎えることも多いです。
125cc小型バイク
125ccの原付二種バイクの寿命目安は5万km前後ですが、定期的なメンテナンスを怠ると、3万km程度で寿命になる場合もあります。
50ccクラスと同じように、エンジンを高回転まで回して走行する機会も多いため、250ccクラスの中型バイクなどに比べ、寿命も短いです。
125ccクラスは50ccクラス同様に、近場の走行に使われることも多く、渋滞の多い地域で日常的に乗っている場合は、発進と停止を繰り返すのでさらに寿命が短くなることもあります。
250cc中型バイク
250cc~400ccまでの中型バイクの寿命目安は、5万km~8万km前後ですが、オイル交換を定期的に行わないなど、メンテナンスを怠ると3万km程度で寿命がくることも。
50ccや125ccクラスに比べエンジンの性能に余裕があり、常に高回転まで回して走行することがないので、エンジンへの負担が少なくなり、寿命も長くなる傾向にあります。
普段から急のつく運転を避け、オイル交換や洗車などの定期的なメンテナンスも怠らなければ、10万kmを走破することもできるでしょう。
400cc~大型バイク
排気量が400ccを超える大型クラスバイクの寿命は、~750ccクラスが5万km~8万kmと中型バイクと同じで、750ccを超えるバイクは8万km~10万kmが寿命の目安です。
中でも1,000ccを超えるリッターバイクは、重いエンジンを搭載するために各パーツも強固なものが使われていることが多く、10万km前後まで走行できるでしょう。
ただし、日頃からしっかりメンテナンスを行っている場合も寿命で、さらにワインディングやサーキットなどスポーツ走行を頻繁に行っている場合は、上記の走行距離の6割~7割程度が寿命の目安です。
2ストエンジン車
2ストエンジンを搭載したバイクは、エンジンの構造から4ストエンジンより寿命が短い傾向にあり、1万km~3万km前後が寿命の目安です。
NSR250Rなどのレーサーレプリカの場合、スポーツ走行を行ってきたバイクは、1万kmを超えたらエンジンのオーバーホールを考えましょう。
50ccのスクータータイプは、メンテナンスの知識があまり無い方が乗っていたケースも多く、1万km前後で寿命を迎えることもあります。
2スト車の注意点
2024年現在では2スト車の新車販売がされておらず、これから2スト車の購入を考えている方は、中古車を求めることになります。
2スト車は生産終了からすでに30年近く経過しており、購入して故障が起きた場合に、修理パーツが手に入らないことも。
まだ中古部品で入手可能なこともありますが、走行に必須のパーツが破損するとバイクに乗れなくなる可能性があるので、走行距離による寿命に加え、パーツの寿命も考えて購入する必要があります。
走行距離が多いバイクを長持ちさせる乗り方

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/AF-7086569/
バイクの走行距離が多くなってきた場合や、多走行の中古バイクを購入した場合など、走行距離が多いバイクの寿命を延ばす方法はいくつかあります。
走行距離が増えたバイクであっても、この先も大切に乗っていきたいと思っている方は、以下のことを意識してバイクに乗ってみてください。
定期的なメンテナンス
バイクに乗る前は走行前点検が義務付けられていますが、ほかにもオイル交換や洗車など、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、バイクの寿命が延びます。
特に走行距離の多いバイクは、オイルシールなどが硬化してオイル漏れを起こすこともあるので、フロントフォークやエンジン周りに、オイルなどによる濡れがないかも点検で確認しましょう。
洗車を定期的に行うと、バイクの細部にまで目が行き届き、オイル漏れなどの発見にもつながるので、洗車もこまめに行うのがオススメです。
エンジンのウォームアップ
エンジンを始動したら、いきなりアクセルを大きく開けて走行せず、少しずつ回転を上げてウォームアップをしましょう。
起きていきなり全力で走れないように、バイクもエンジン始動直後からアクセルを大きく開けて走ると負担が大きく、寿命を縮める結果に。
特に気温の低い冬場に乗る場合は、できれば走行前に5分程度暖機運転を行い、走行し始めは少しずつエンジンの回転数を上げていくようにすると、エンジンへの負担も減らせます。
屋内保管
バイクは雨の中を走行できるように作られているので、屋外で保管(駐輪)しておけますが、寿命を少しでも延ばしたいなら、屋根のある屋内での保管が望ましいです。
バイクを構成するパーツの多くは金属製で、雨ざらしにしておくと、雨やほこりなどの影響を受けてサビが発生しやすくなります。
また、直射日光の中においておくとプラスチックなどの樹脂製パーツや、シールなどのゴム製パーツの劣化も進みやすくなるので、できるだけ屋内で保管するようにしましょう。
部品交換
バイクの部品の中には、定期的な交換が必要なパーツがあり、それらを交換していくことで、バイクの状態を保つことができます。
交換が必要なおもなパーツは、ブレーキパッドやチェーン、スプロケット、クラッチなどです。
急ブレーキや急加速など、急のつく運転をくり返していると、消耗品の寿命も短くなるので、丁寧に運転をすることで消耗パーツの寿命も延びます。
丁寧な運転
度々出ていますが、「急」のつく運転(急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど)を控えて丁寧に運転をすれば、バイクへの負担も減って寿命が延びます。
バイクに負担がかかる運転を続けていると、消耗部品の交換サイクルも短くなり、燃費の悪化にもつながるのでお財布にも厳しいです。
急のつく運転を避け、丁寧な運転をすれば消耗部品の交換サイクルも長くなり、安全運転につながるうえ、違反運転で警察に取り締まりを受けることも避けられます。
エンジンオイル交換(3,000km~5,000km目安)
エンジンオイルには、バイクの心臓でもあるエンジンを保護し、潤滑をよくしてスムーズな燃焼にする役割があります。
バイクの乗り方にもよりますが、街乗りメインの乗っている場合は、3,000km~5,000km毎でのオイル交換が目安です。
高回転を回すことが多いスポーツ走行や高速道路を多用する場合は、3,000kmでの交換がおすすめですが、定期的なオイル交換はエンジンの寿命を延ばすことにつながります。
また、オイル交換の際に一緒にオイルフィルターも交換をすると、よりエンジンを保護できて効果的です。
チェーン・ブレーキパッドの点検(5,000km~1万km目安)
バイクのチェーンはスプロケットを介して、エンジンで生まれた回転力をタイヤに伝える役割がありますが、常にスプロケットに接しているため、定期的なオイル注油が必要です。
また、常に外に出ているチェーンはほこりなどのゴミが付着しやすいため、1,500km~2,000km毎に清掃を行い、異物を取り除いたあと注油をしましょう。
ブレーキパッドもバイクを制動させる重要部品で、5,000kmを超えたら交換が必要になりますが、交換時期はブレーキパッドの溝で確認できます。
ブレーキパッド交換時期の目安
バイクのブレーキパッドは、5,000km~1万kmが交換時期の目安ですが、運転の仕方や走行環境によっても交換時期が変わってきます。
交換時期はブレーキパッドに掘られている溝の残りで判断でき、残り溝が5mm以上あればまだ交換は不要ですが、効きが悪いと思ったら新品に交換してください。
残り溝が3mmになったらできるだけ早く交換が必要で、1mm以下になるとすぐにでも交換が必要となり、交換をせずに走行していると、ブレーキローターにダメージを与えることもあります。
スプロケットやクラッチなど主要部品の交換(1万km~3万km目安)
スプロケット(スプロケ)はチェーン駆動しているギア状のパーツで、フロント(エンジン側)と、リア側の2つがあります。
フロントのほうが交換時期は短く、おおむね1万km~2万kmが交換時期の目安で、リアは3万kmが交換の目安です。
また、ミッションのバイクはクラッチ交換も必要で、2万km~3万kmが交換時期の目安ですが、半クラッチが多いなど乗り方によっては2万km以下で寿命になることもあります。
中古バイクを選ぶ際の走行距離目安

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/AF-6615392/
3万km以下の走行距離であれば、比較的バイクの状態が良いとされており、5万kmを越えると、エンジンのオーバーホールや、部品の交換が必要になる場合が増えます。
走行距離ごとの目安を、走行距離ごとに詳しく解説していきますので、中古バイクの購入を考えている方は、参考にしてみてください。
5,000km以下
バイクの走行距離が5,000km未満の場合、コンディションが良い状態のものが多いです。
交換部品がほぼ必要なく、購入したらそのまま乗れる状態のバイクがほとんどでしょう。
走行距離が2,000km程度で登録から1年以内のバイクであれば、ほぼ新品状態のバイクとして乗れます。
10,000km以下
比較的状態のよいのが1万km以下のバイクで、メンテナンスもそれほど必要としないでしょう。
消耗品の交換が必要な場合でも、最低限の交換で済むケースが多く、費用の負担もそれほど多くかからない場合も多いです。
ただし原付クラスの場合は、1万km近くになると交換するパーツが多くなってきたり、バイクによってはエンジンのヘタりが出てきたりします。
20,000km以下
2万km以下のバイクは走行距離も多く、クラッチ交換やチェーン交換など、メンテナンスに予算が必要になってきます。
購入した後に消耗品の交換が必要になることもあるので、消耗品の交換を想定し、ある程度メンテナンス費用を用意しておきましょう。
バイクによってはエンジンの調子が今ひとつなど、個体によってコンディションの差が大きく出てくる走行距離です。
30,000km以下
走行距離が3万km以下になると、バイクによっては非常に安価で購入できます。
ただし、コンディションの期待もできず、購入後に多くのメンテナンス費用が必要になることもあり、結果として高くついてしまったということも。
バイクによってコンディションの差が大きく、相場より極端に安いバイクは、不具合が出る可能性が高いです。
50,000km以上
5万km以上の走行距離になると、1万kmを走らずに寿命となるバイクも出てきます。
人気車種は5万kmを超えていてもしっかり値段が付いていることも多いですが、不人気車の場合は捨て値のような値段で買えることも。
乗っていた人の扱いやメンテナンスの頻度などにより、バイクのコンディションは大きく変わりますが、整備点検簿などの記録が残っていれば、大事に乗られていた可能性があります。
バイクの走行距離が増えると燃費や加速性能に影響が出る?

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/82-8109453/
結論から言えば、走行距離が増えると燃費や性能に影響が出ますが、理由は走行距離が増えるとスプロケットやクラッチなどの摩耗が進み、駆動にロスが生じるようになるためです。
ほかにも、タイヤやチェーンの状態によっては燃費や加速性能に影響が出ます。
タイヤの摩耗
タイヤが摩耗していたり、空気圧が適正でなかったりすると、タイヤが転がる際に抵抗が増え、燃費や加速性能に影響が出ます。
燃費や加速性能が悪くなってきたと感じるようになったら、タイヤの摩耗していないか、空気圧が適正かをチェックしてみましょう。
チェーンの状態
タイヤの点検と同時に、チェーンが垂れすぎていないか、スプロケットの摩耗が進んでいないかもチェックするのがオススメです。
シャフトドライブ以外のバイクはチェーンを介してリアタイヤを回していますが、走行距離が増えるとチェーンが伸びて、駆動力をリアタイヤに伝えるときにロスが生じるようになります。
チェーンが伸びていると走行中に外れる危険性もあるので、チェーンの遊びを適正にするか、新品に交換しましょう。
まとめ

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/82-8029595/
バイクの走行距離と寿命の関係について、排気量ごとに寿命の目安となる走行距離を解説するとともに、寿命を延ばす方法についても解説してきました。
また、中古車で購入を考えている方に向け、走行距離ごとの状態や注意点も解説していますので、購入の際の参考にしてみてください。
走行距離が伸びてくると消耗品の交換が必要となるので、1万kmを超えるバイクを購入する場合は、メンテナンス費用も予算に入れておくと、購入後も安心です
おすすめ商品
PR
最新記事
-
2025年11月12日バイクミラーの正しい調整方法!ズレる・グラつく場合の対処法も解説
-
2025年11月12日バイクでウエストバッグが危ないと言われる理由!対処方と安全性の高い商品も紹介
-
2025年10月17日【状況別】バイクの燃料コックはどの向きにすればいい?各向きの役割とトラブルも交えて解説
-
2025年10月17日バイクのヘルメットに関する法律をわかりやすく解説!違反例も掲載
-
2025年9月4日バイク洗車の正しいやり方をステップで解説!必要な道具と注意点も解説
-
2025年9月4日バイクの盗難対策やりすぎてない?メリットやデメリットと適切な対策ラインを解説
-
2025年9月3日バイクのローダウンのメリット・デメリット!方法や費用についても解説
-
2025年9月3日バイクのリチウムイオンバッテリーのメリット・デメリット!鉛バッテリーとの比較表も
-
2025年9月2日バイク乗りの「ヤエー」って何?賛否が分かれるライダーの挨拶