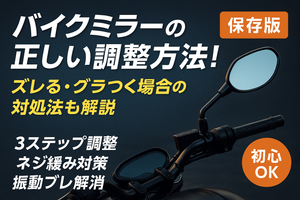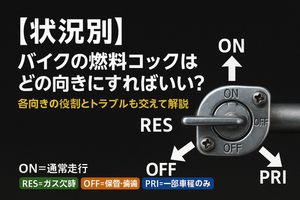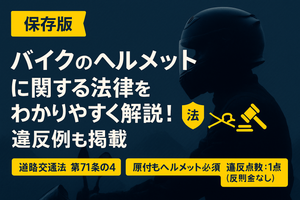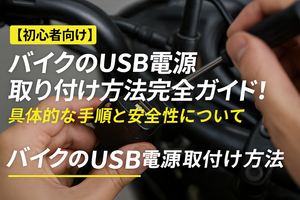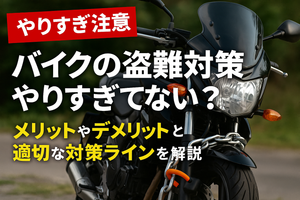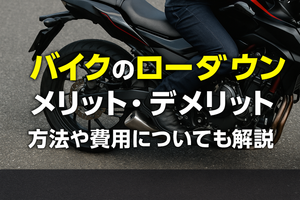バイクのヒューズが切れる原因と対処法!よくある6つのケースと応急処置

バイクのヒューズが切れる原因① 配線のショート

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/A4-407175/
バイクのヒューズを交換しても、またすぐに切れてしまう場合は、いくつかの原因が考えられます。
ヒューズとは、電流(電気の流れ)に何らかの異常が発生して過電流になった場合に、切れて電流を遮断するパーツのことで、電気に関わるパーツを過電流から保護する役割です。
症状
ヒューズを交換してもすぐに切れるような場合や、スイッチをONにした瞬間にヒューズが飛ぶような症状が起こることがあります。
また、突然ヘッドライトが消えたり、ウインカーが付かなくなったり、ホーンが使えなくなる症状も。
ヒューズは過電流の保護が目的で、過電流になっている原因を解決しなければ、新しいヒューズに交換しても、すぐに切れたり切れやすかったりします。まずはヒューズが切れる要因を調べましょう。
配線のショートが起こる要因
ヒューズがすぐに切れたり、突然飛んでしまったりする症状の原因は、経年劣化で配線が断線しかかっていて、電流が正常になっていないことがあります。
自分でカスタムした場合に多いですが、配線のミスや電装品を取り付けたときに、配線の接続が甘くかったり、ほかの配線と接触したりしているケースも。
あとは配線を保護し絶縁しているビニールカバー等が破れ、フレームやほかの配線、パーツなどに接触して、電気の流れに異常がある場合もヒューズ切れが起こります。
対処法
ヒューズがよく切れる場合は、以下の手順を試してみましょう。
手順1:配線の目視チェック
ヒューズがよく切れる場合の対処法として、まずはヒューズがまとめて収納されている「ヒューズボックス」を開け、どの電装パーツに関係したヒューズが切れているのかを確認します。
ほとんどのバイクは、シートの下やカウル内にヒューズボックスがありますが、位置が分からない場合は取扱説明書で確認をしましょう。
ヒューズを確認する際、例えばライト用のヒューズが切れていたら、ヘッドライト周辺の配線を目視で重点的に調べ、配線の被膜が破れていないか確認をします。
特にガソリンタンク下やフレームと接触している部分、エンジン周りの配線は振動で断線しやすいので、より重点的に確認してみましょう。
手順2:マルチメーターでショート箇所を探す
目視でも配線の異常場所が特定できない場合や、より的確に異常場所を確認したい場合は、マルチメーター(テスター)を使ってショートした部分を探します。
マルチメーターは電流・電圧の測定や通電しているかどうかを判定するアイテムで、使う場合は作業中のショートを防ぐため、まずはバッテリーを外してから使用しましょう。
ヒューズが切れた電装関連の配線を、マルチメーターの導通チェックモードで調べ、断線していないかチェックします。
また、ヒューズ端子の片側とフレーム(アース)間の抵抗を測り、ゼロに近い場合はショートの可能性が高いです。
手順3:ショートしている部分を修理
ショートしている箇所の特定ができたら、配線の補修や交換を行っていきますが、配線が破れている場合は、絶縁性のある自己融着テープや熱収縮チューブで補修していきましょう。
配線が接触しているのなら、プラスチックカバーやスポンジを接触箇所の間に挟み、振動で外れ落ちないように固定しておきます。
明らかに配線が損傷・断線している場合は、ギボシを使って新しい配線でバイパス(迂回配線)を行うか、ハンダで補修しその上から絶縁テープを巻きましょう。
バイクのヒューズが切れる原因② 過負荷

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/B3-3207284/
バイクのヒューズが切れる原因の一つに、電流に異常が発生し過負荷となっているケースがあります。
過負荷になるとどういった症状が起きるのか、詳しい症状と原因について見ていきましょう。
症状
電流に何らかの異常が生じ過負荷となると、エンジンをかけた直後や、複数の電装品(グリップヒーターやフォグランプなど)を使ったときに、ヒューズが飛びます。
また、グリップヒーターやフォグランプ、USB充電器などの電装品を追加してから、頻繁にヒューズが飛ぶ症状も出やすいです。
過負荷が起きると、目に見えた症状としては分かりにくいですが、電力を安定させる役割のレギュレーターにストレスがかかり、故障の原因にもつながります。
過負荷が起こる要因
過負荷は、ホーンを社外品に交換した際に消費電力が上がったり、USB電源を増設してスマホやカメラなどを受電したりした場合に起きやすいです。
ほかにも、LEDライトやフォグランプを後付で増設したり、グリップヒーターや電熱ジャケットを追加したりした場合も、過負荷が起きやすくなります。
電装品を必要以上に追加するなど、電装品の消費電力の総量がヒューズやバッテリーの定格を超えてしまうと、過負荷が起こりやすいのです。
対処法
過負荷が原因でヒューズが飛ぶ場合は、次の手順を試してみてください。
手順1:追加した電装品の消費電力を計算
電装品の総消費電力が、ヒューズの許容範囲内(定格)に収まるようにしましょう。
各電装品の消費電力(W)を確認し、消費電力(W) ÷ 電圧(V) = 消費電流(A)を計算、合計の電流値がヒューズの定格を超えていないかチェックしましょう。
(例)12Vのバイクに60Wのフォグランプを追加すると、60W÷12V=5A(アンペア)となりますので、電装品の電流(A)を算出し、合算して総消費電流を出します。
手順2:リレーを追加して電流負荷を分散
大電流を必要とする電装品の場合、ヒューズ直結にならないようリレーを経由して接続し、電流の負荷を分散させるようにしましょう。
また、バッテリーから直接電源を取るのも効果的なので、そちらも検討してみてください。
手順3:適切なヒューズに交換
電装品を追加した際、付いているヒューズの容量がギリギリなら、1ランク上のアンペアに交換するのも手です。(10A→15Aに交換)
ただし、大幅にアンペアを上げると配線が焼け、ショートする可能性が高いので、容量アップは1ランク上にとどめましょう。
バイクのヒューズが切れる原因③ バッテリーの逆接続

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/8A-791333/
バッテリーの端子を取り外したあと、端子の接続を誤って逆に接続すると、メインヒューズが切れます。
そのようなミスをした場合に、しっかり働いてくれるのがヒューズの効果でもあります。
症状
バッテリーの端子をプラス・マイナス逆に接続すると、メインヒューズが一瞬で切れます。
メインヒューズが切れると、全ての電装品が動かなくなりますが、メインヒューズを交換すれば復活するケースも多いです。
バッテリー逆接続がおこる要因
バッテリー交換時や、端子を取り外して電装品を追加したときに起きやすいのが、プラス・マイナス端子を逆に接続してしまうことです。
端子を逆に接続すると、メインヒューズが切れて電装回路を保護してくれますが、ECUやレギュレーターを壊すことがあります。
対処法
バッテリーを逆に接続してしまったら、速やかに端子を外し、メインヒューズが切れていないか確認しましょう。
メインヒューズが切れている場合は、新しいものに交換(通常は30Aか40A)し、バッテリーの端子を正しく接続しましょう。
まれにバッテリー逆接続で、ECUやレギュレーターを壊してしまうことがあるので、バイクショップで診断してもらうのが無難です。
バイクのヒューズが切れる原因④ レギュレーターの故障(発電異常)

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/B8-2651286/
レギュレーターの故障により、発電異常や電圧が安定しなくなり、ヒューズが切れることがあります。
レギュレーターは電装系が安定して働けるよう、電圧の安定化を図るパーツなので、故障すると電装回りにトラブルが発生することも。
症状
レギュレーターに不具合が生じると、ヘッドライトの明るさが不安定になり、ウインカーを付けるとウインカーの点灯に連動し、ヘッドライトの明るさが変わるなどの症状が起きます。
バッテリーも上がりやすくなり、故障しているとバイクを停車して買い物を済ませ、再度エンジンを始動しようとしたらかからない、といった症状に。
また、エンジンを掛けるとヒューズが飛び、新しいジューズに交換しても、またすぐに飛んでしまうことが起きます。
レギュレーターの故障(発電異常)が起こる要因
レギュレーターは過電流が流れたり、熱や振動による劣化で壊れたりすることがあり、ヒューズ切れの原因にもなります。
配線の接続不良や断線によって過電流が発生し、レギュレーターにストレスを与えて、故障が発生することも。
対処法
レギュレーターが正常かどうかは、エンジンOFF時にバッテリーの電圧を測定し、12.5V前後の電圧があれば正常の可能性が高いです。
エンジンON時にバッテリーの電圧を測定(アイドリングが安定してから)し、正常なら13.5V~14.5V前後の電圧となりますが、アイドリングからエンジン回転数を上げ、15V以上になるなら故障の可能性があります。
レギュレーターの故障が認められる場合は、信頼のおけるバイクショップで交換してもらいましょう。(部品代:8,000円~11,000円前後、交換工賃:2,000円前後~)
バイクのヒューズが切れる原因⑤ ヒューズの劣化

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/97-948974/
経年劣化などでヒューズが劣化していると、突然切れることがあります。
劣化でヒューズが切れる前に点検で予兆を発見できることもあるので、たまにヒューズも点検をしてみましょう。
症状
ヒューズが劣化していると、特に不具合や異常が見当たらないのに、突然ヒューズが切れることがあります。
また、ヒューズを確認すると金属の接触部分が変色してくすんでいたり、錆びていたりする場合は劣化しているので、早めの交換が必要です。
ヒューズ劣化が起きる要因
ヒューズの劣化が起きる原因として、湿気によって錆が発生して腐食したり、金属の接触部分がくすんで、電気が通りにくくなったりするケースがあります。
古いヒューズは知らない間に劣化が進み、突然切れることがあるため、長年ヒューズ交換をしていない場合は要注意です。
また、走行中の振動やエンジンの振動などで、接触不良を起こしていることもあります。
対処法
経年劣化や錆などでヒューズが切れる前に、全てのヒューズを定期的に点検し、接続部分がくすんでいたり錆が発生していたりする場合は、新しいヒューズに交換しましょう。
端子部を接点復活剤で清掃を行うのも効果的ですが、万が一切れたときに備えて、予備のヒューズを持っておくのもオススメです。
バイクのヒューズが切れる原因⑥ 配線の接触不良

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/B8-7006472/
バイクのヒューズが切れる原因に、配線が接触不良を起こしているケースがあります。
配線の被膜が破れ、中の配線がむき出しになったり、配線が周辺に接触したりして、ショートしている可能性があります。
症状
配線の接触不良や異常がある場合、走行中の振動で電装品が動いたり動かなくなったり、ときに消えるなどの症状が起きます。
ウインカーを出した場合など、特定の操作をするとヒューズが飛び、電装品が急に使えなくなった場合も配線が接触不良を起こしている可能性が高いです。
配線の接触不良がおきる要因
配線の接触不良が起きる要因は、経年劣化で配線が傷み接触不良になるケースが多いです。
また、自分で電装品を取り付けた際、配線のギボシ端子のかしめが甘いなど、接点がしっかり接触していないこともあります。
カプラーや端子が外れ掛かり、振動で接触不良を起こすこともあり、そのような状態だと電装まわりの動作が不安定です。
対処法
接触不良によるヒューズ切れを防ぐには、ヒューズボックス周辺のカプラーが緩んでいないか、自分で配線を行っているなら、接続した配線回りに緩みや接触不良が起きていないか確認しましょう。
接触不良が疑われる箇所や、自分で新たに配線を行った箇所は界面活性剤を塗布し、接触不良を防ぎましょう。
配線が振動すると接点から接触不良が起きやすいので、できるだけ配線を結束バンドやクッション材で固定し、振動で緩まないようにすると接触不良が予防できます。
ヒューズが切れたときの応急処置

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/86-407186/
ヒューズが切れてすぐにバイクショップへ持ち込めない場合や、ツーリングの途中など、緊急で対応しないといけない場面があります。
そんなときは予備のヒューズがあれば、応急処置を行えば走行できるようになることもありますが、できるだけ早く断線などのチェックを行うか、バイクショップで点検してもらいましょう。
予備のヒューズ(同じアンペアのもの)と交換
予備のヒューズを持っている場合は、切れたヒューズと同じアンペア(A)のヒューズに差し替えれば再び通電し、バイクが動くようになります。
交換の手順はヒューズボックスにある切れたヒューズを指やピンセットなどで抜き、新しいヒューズに交換(差し込む)するだけです。
ヒューズ交換の注意点として、必ず同じアンペアのヒューズに交換する点で、例えば10Aのヒューズが切れたから20Aに交換、というのはトラブルの原因になります。
ただし、ヒューズ交換をしてもすぐに切れる場合は、ショートや配線トラブルの可能性があるので、無理に動かさずに救援を要請しましょう。
予備のヒューズがない場合
ツーリング中などすぐに点検や修理できない状況にある場合は、以下の方法で一時的に復旧させることができます。(あくまでの応急なので、できるだけ早く点検・修理を行ってください)
応急処置として、別のヒューズを一時的に使い回す方法があり、例えば走行に影響のないグリップヒーターやシガーソケットのヒューズを交換し、重要な回路のヒューズに当てるなどです。
交換するヒューズは必ず同じアンペア(A)のものにしますが、絶対にやってはいけないことは、アルミホイルや針金を巻いて代用したり、高すぎるアンペアのヒューズを使ったりすることです。
アルミホイルや針金を使うと過電流が流れたときに、ショートして燃える危険性があり、高すぎるアンペアのヒューズは、配線が焼けてより大きな故障につながる可能性があります。
すぐに走行しない場合はロードサービスを呼ぶ
予備のヒューズがなく、原因の特定ができない場合は無理にバイクを走らせず、ロードサービスやバイクショップに引き取りに来てもらうのが安全です。
ショートや過負荷が原因なら、配線や電装関連のパーツに異常がある可能性があるので、ヒューズを交換しても、またすぐに切れてしまい事故につながる可能性もあります。
JAF会員なら無料でバイクを引き上げ、近くのバイクショップなど任意の場所に搬送してくれるので(20Kmまで無料)、加入している場合はJAFに救援を要請するのがオススメです。
おすすめ商品
PR
最新記事
-
2025年11月12日バイクミラーの正しい調整方法!ズレる・グラつく場合の対処法も解説
-
2025年11月12日バイクでウエストバッグが危ないと言われる理由!対処方と安全性の高い商品も紹介
-
2025年10月17日【状況別】バイクの燃料コックはどの向きにすればいい?各向きの役割とトラブルも交えて解説
-
2025年10月17日バイクのヘルメットに関する法律をわかりやすく解説!違反例も掲載
-
2025年9月4日バイク洗車の正しいやり方をステップで解説!必要な道具と注意点も解説
-
2025年9月4日バイクの盗難対策やりすぎてない?メリットやデメリットと適切な対策ラインを解説
-
2025年9月3日バイクのローダウンのメリット・デメリット!方法や費用についても解説
-
2025年9月3日バイクのリチウムイオンバッテリーのメリット・デメリット!鉛バッテリーとの比較表も
-
2025年9月2日バイク乗りの「ヤエー」って何?賛否が分かれるライダーの挨拶